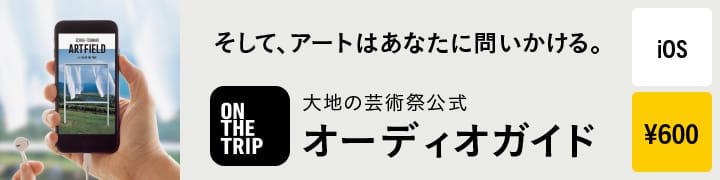物語 / 私と「大地の芸術祭」第1回(前編)
「勘違い上等!」なアート体験のススメ

モデル / 「大地の芸術祭」オフィシャルサポーター
田中里奈さん
「大地の芸術祭」は、地元の方々はもちろん、多様なサポーターに支えられて成長してきました。本連載では、そのサポーターの皆さんの視点でこの芸術祭を語っていただきます。今回のゲストは、モデルの田中里奈さん。「大地の芸術祭」オフィシャルサポーターでもあり、さまざまなメディアを通してこの芸術祭の魅力を発信しています。そこで、彼女のアートとの出会いから、好きな作品、この芸術祭の楽しみ方までをたっぷりと伺いました。
テキスト:中島晴矢 撮影:豊島望 編集:内田伸一、宮原朋之(CINRA.NET編集部)
あなたにとって大地の芸術祭とは?
「肩書き」を取り払って、純粋にひとりの人間としていられる、心の故郷みたいな存在。
27 September 2019
アートの楽しみ方の発見
マ・ヤンソン/MAD アーキテクツ「Tunnel of Light」2018年(撮影:中村脩)
ファッションモデルのみならず、ブランドとのコラボレーションや書籍の出版など、多彩に活躍する田中里奈さん。そんな彼女がアートに目覚めたのは、大学生の時に行った「瀬戸内国際芸術祭」がきっかけだったと言います。

もともと小さい頃から、絵を描いたりものを作ったりするのは好きでした。でも大人になるにつれて、「アートは美術館に鑑賞しに行くもの」「美術の知識がないとわからないもの」と思うようになっていたんです。それで、興味はあるけど、自分とは遠い敷居の高いものだと感じる時期がありました。そんな時に「瀬戸内国際芸術祭」で直島に行ってみたら、すごく楽しくて。「アートって、その場で感じて楽しめるものなんだ!」と、価値観ががらっと変わりました。
それからアートを身近に感じるようになったという田中さんは、「私は批評家ではないから、あくまで自分自身の感覚を大切にしたい」と語ります。

それまでは、学校の勉強みたいに答えがある問いに慣れていました。でも、アートに正解はありませんよね。私は旅行も趣味なのですが、旅だって、みんなと同じ答えや真実をインストールしに行くわけじゃありません。「それぞれの感性で遠慮なく勘違いしていいんだ」と思えるようになってから、アートを素直に楽しめるようになりました。
「勘違い上等!」と笑う田中さんはその後、知り合いだった「大地の芸術祭」オフィシャルサポーター・リーダーの高島宏平さん(オイシックス・ラ・大地株式会社代表取締役社長)に誘われて、予備知識なく越後妻有の地を訪れたそうです。

新潟の山の中にこんな大規模な芸術祭があるんだと知ってびっくりしました。瀬戸内の魅力が「広がる海の開放感」なら、越後妻有には「心の故郷」のような空気感がありますね。山々を越えて入っていくと、大自然に護られた雰囲気が温かい。何回だって行きたくなる場所です。
「大地の芸術祭」のお気に入り作品
関根哲男「帰ってきた赤ふん少年」2009年(撮影:中村脩)
越後妻有に足を運ぶたびに思い出が増えていったという田中さんに、お気に入りの作品を教えてもらいました。

真っ先に「またこの芸術祭に来たなぁ」という気持ちにさせてくれるのが、小荒戸集落にある「帰ってきた赤ふん少年」。お地蔵さんみたいに急に現れるのがいいし、冬場は服を着せちゃうアートなんて、可愛すぎません?
_MG_0405.jpg)
関根哲男「帰ってきた赤ふん少年」2009年(撮影:中村脩)
渋海川沿いに並ぶ、40人の赤ふん少年。2006年に同じ場所に展開した作品が、集落の要望に応えて「帰ってきた」。木彫をバーナーで焼くことで、健康的に日焼けした少年に。かつて渋海川の水は澄んでいて滝つぼもあり、小荒戸集落の男性は、少年時代に赤ふん姿で渋海川を泳いだ記憶がある。今回は、自然木によるひときわ大きな「赤ふん大将」が登場し、集落のシンボルとなった。手ぬぐいを巻いた姿もユーモラス。

2018年(第7回)に大好きになったのは、閉校した中学校の教室に設置されたニコラ・ダロさんの「上郷バンドー四季の歌」でした。動物や妖怪の姿をした人形たちがバンドの演奏をするんです。舞台の作りも細部の動きもすごく巧妙で、ずっと見ていたいくらい心地いい作品ですね。家にほしい!

ニコラ・ダロ「上郷バンドー四季の歌」2018年(撮影:木奥惠三)
閉校した旧上郷中学校の教室に、古民家を象った舞台を制作。天井からは地域の象徴である雪をイメージした布が上下し、動物の姿をした自動人形が「上郷バンド」を組み、地域の人々へのヒアリングをもとに制作した曲を演奏する。物語の世界を作りだす、劇場型の作品。

芸術祭の歩みの中では、今は無くなってしまった作品もあるけど、神社に展示されたエマ・マリグさんの「アトラスの哀歌」は大好きでしたね。地球儀のような球体がくるくる回っていて、まるで影絵のよう。すごく綺麗でした。また、拝殿の中という普段入れない場所に入るというちょっとした背徳感に、より一層ドキドキしました。

エマ・マリグ「アトラスの哀歌」中条・高龗神社 2018年(撮影:中村脩)
政変により17 歳で国外亡命を経験し、アーティストであり旅人でもあると自称する作者が、放浪・亡命・移動をテーマにした作品を制作。紙とガーゼを用いて繊細ではかない地球儀を作り、そこに言葉を刻んでいく。光と音で彩られた作品は、故国チリへのノスタルジアを常に抱き続ける作者の心情を反映している。
また、田中さんにとっての「大地の芸術祭」は、作品ばかりではなく、宿泊もまた記憶に残る体験だったそうです。

おすすめは、木造校舎が宿泊施設になった三省ハウスです。友達と一緒に行けば、まるで「大人の修学旅行」。大人になってから二段ベッドがいっぱいある部屋で寝るなんて、めったにできない経験ですよね。食事は集落のお母さんたちの家庭料理で、談話室にレアンドロ・エルリッヒの作品があったり、体育館で遊べたり。これで楽しくないわけがない!(参考:アートと共に滞在する。三省ハウスで過ごすひととき)

三省(さんしょう)ハウス *現在は10名以上の団体利用のみ受け付けています。(撮影:野口浩史)

こんな風に、自然の中や廃校の教室、神社、古民家といった、人の気配があまりしないような場所や、逆に人の温もりにふれる場所にアートがあるんですよ。だから、調和していないようで調和している、なんとも言えない異空間が出来上がっているんだと思います。それって、美術館では味わえない魅力ですよね。そこに、この芸術祭ならではの面白さがあるんじゃないでしょうか。
自分の感性を通して、芸術祭を思う存分に満喫している田中さん。後編では、彼女の務める「大地の芸術祭」オフィシャルサポーターとしての活動について、お話を伺っていきます。