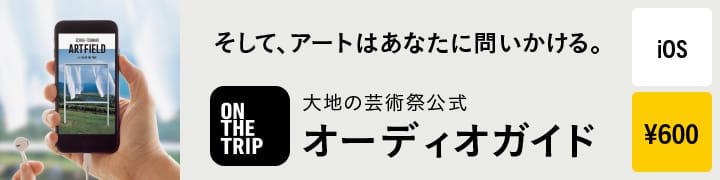物語 / 私と「大地の芸術祭」第4回(前編)
「大地の芸術祭」に惚れ込んだ、3つの大きな衝撃体験

アソビュー株式会社 代表取締役CEO / 「大地の芸術祭」オフィシャルサポーター
山野智久さん
「大地の芸術祭」を支える多彩な人々に迫るこの連載。今回のゲストは、週末の便利でお得な遊び予約サイト「アソビュー!」で知られる、アソビュー株式会社の山野智久 CEOです。デジタル領域の敏腕経営者にして、「大地の芸術祭」オフィシャルサポーターでもある彼。クールな人物像を想像していましたが、実際はとても熱い人でした。
テキスト:内田伸一 撮影:豊島望 編集:内田伸一、宮原朋之、川浦慧(CINRA.NET編集部)
あなたにとって大地の芸術祭とは?
ロジックではなく、ハート。
20 February 2020
経済合理性だけでは答えが出ない世界で
棚田が広がる星峠(新潟県十日町市)の風景 画像提供:(一社)十日町市観光協会
「アソビュー!」は、全国のアウトドアスポーツやものづくり体験、遊園地や温泉など、多様な体験やチケットをネットで予約・購入できる「遊びのマーケットプレイス」。モノではなく体験の豊かさを求める人々から、多くの支持を得ています。「大地の芸術祭」のチケットやツアーも扱うほか、これらを芸術祭公式サイト上から申し込める仕組みも支えてくれています。実はこのWEBマガジン『美術は大地から』の観光カテゴリー記事を担当しているのも、「アソビュー!」を運営するアソビュー株式会社の「あそびのプロ」と言える皆さんです。

「アソビュー!」は全国の「遊び」体験を予約できる人気ウェブサービス。2012年のリリース以降、成長を続け、現在2万件以上のプランを掲載する。
山野さんは、そのアソビュー社のCEO。彼の経歴をひも解くと、大学生時代に立ち上げた、地元の魅力を紹介するフリーペーパーを発行部数30万のメディアに成長させ、卒業後はリクルート社で新規事業立ち上げなどに関わった後、独立してアソビュー社を立ち上げました。若くして起業家の道を歩んできた山野さんにとって、芸術とはどんな存在なのでしょうか?

アートに興味があり、海外に行くときなどは現地の美術館を訪ねます。その国の背景にふれたいのと、仕事柄、レジャースポットとしての魅力も知りたいというのが主な動機です。一方で、仕事で悩むとふらっと近くの美術館に行き、自分にとって「よくわからない」ものにふれてきました。ビジネスは基本的に、経済合理性(投資したお金に対して利益があると考えられる状態)から解を求める世界です。でも、それだけでは答えを得られないことも多い。自分の頭のOSだけを頼ると気付けないこともある。だから僕にとって芸術は、自分の中のバランスを整え、物事の本質を見極めるためにも大切だと思っています。

山野さんも一員の「大地の芸術祭」オフィシャルサポーターは、各界で活躍中の人々からなる芸術祭の応援団的存在。写真はオフィシャルサポーターと行く芸術祭ツアーの様子。
「大地の芸術祭」との出会いは、先輩経営者であり、有機・無添加食品などの通信販売を行うオイシックス・ラ・大地株式会社の高島宏平代表に誘われてのことだったそうです。なお高島さんは「大地の芸術祭」を運営するNPO法人 越後妻有里山協働機構の副理事長でもあります。

「大地の芸術祭」には、その理念に賛同し、各界からオフィシャルサポーターとして関わっている人たちがいます。この連載の第1回に登場した、モデルの田中里奈さんもそうですね。そのリーダーでもある高島さんに誘われ、冬の越後妻有を訪ねる「大人の遠足ツアー」に参加したのが、「大地の芸術祭」との出会いでした。
「大地の芸術祭」の里で受けた、3つの衝撃
冬には一面の銀世界となる、まつだい雪国農耕文化村センター「農舞台」周辺
初の越後妻有訪問で、山野さんは「3つの衝撃」に出会ったそうです。

1つ目は、そこで初めてふれた芸術のありようです。最初に出会ったのは、バスでの移動中に見つけた、関根哲男さんによる彫刻群「帰ってきた赤ふん少年」。雪の中に半分埋もれて立っていて、最初は「かかし」か何かだと思ったんです。豪雪地帯だから冬は川沿いに移動させているのかな? という感じで、芸術作品だとは気付かなかった。ところがこれも「大地の芸術祭」から生まれた作品で、しかも毎年、冬になると地元の農家の人たちが服を着せてあげているというので二度びっくりしました。
関根哲男「帰ってきた赤ふん少年」2009年(撮影:Osamu Nakamura) 冬になると地元の人々が服を着せてあげるのが習慣となっている。
関根哲男「帰ってきた赤ふん少年」2009年(撮影:Osamu Nakamura) 冬になると地元の人々が服を着せてあげるのが習慣となっている。
この体験は、それまで見てきた芸術とは違う感覚をもたらしたといいます。

美術館での鑑賞しか知らなかった僕は、芸術って面白いけど、遠くから崇めるもので、自分とは真逆にある気もしていました。だからこそ関心があった一面もあるのですが。ただ、ここでは地元のおじちゃんやおばちゃんが、芸術に勝手に服を着せている(笑)。もちろん悪い意味ではなく、自然としてそうしているらしいことが驚きでした。しかも芸術祭側は「それも含めて作品です」と言う。それってすごいなと感動したんです。芸術とは、こんなにも身近に感じられ、かつ変化しながら地域に根付くものなのだなと。
それは、続いて越後妻有で体験した多くの作品にも通じることだったようです。

内海昭子さんの「たくさんの失われた窓のために」や、磯辺行久さんの「川はどこへいった」も、この芸術祭における真骨頂だと思います。美術館という均質空間の中で愛でるものとは違い、自然の景観美や四季の移り変わり、地域の営みや歴史の中に、芸術がシンクロしていく。そして僕らはそれらを調和の中で感じられる。そうして、芸術が観る側の中にも生まれるのだと思えたとき、その真価に対する考えが確実に変わりました。

内海昭子「たくさんの失われた窓のために」2006年(撮影:倉谷拓朴)
それでは、山野さんが越後妻有で受けた2つ目の衝撃とは?

芸術祭を支える多くの人たちの存在です。そのツアーでの食事は、地元のお母さんたちが越冬料理をご馳走してくれる「雪見御膳」というものでした。料理そのものも素晴らしかったのですが、加えて僕がすごいと思ったのは、これらの活動を支えるために大勢が関わっていること。芸術祭が始まると、各地から何百人ものボランティアが参加するとも聞きました。過疎化が進み、労働生産人口も低い地域で、芸術をきっかけに仕事が生まれ、価値あるものに対しては無償で関わる動きも生まれている。そのことに感銘を受けました。

「雪見御膳」は冬の越後妻有ツアー限定の郷土料理プログラム(撮影:Osamu Nakamura)
そして、最後の3つ目の衝撃は、形はなくとも感じられるものでした。

行く先々で出会う地域の方々が、本当に嬉しそうだったんですね。この芸術祭に関わる喜びと誇りを皆さんから感じたし、当初は総合ディレクターの北川フラムさんが自ら地域での説明会を何百回と開いたことなどを聞くにつけ、重ねてきた努力も知りました。アソビューも事業を通じた「地方創生」をテーマのひとつにしていますが、こんなにも泥臭く、しかし温かく成果を出している地方創生があるのだなと。思い返すと、この3つの衝撃を通して芸術祭に惚れ込んでいった感じですね。
その後、高島さんの勧めを受けてオフィシャルサポーターに仲間入りした山野さん。「実は最初は、末席の幽霊部員程度に考えていたけれど、順調に巻き込まれていきました(苦笑)」とおどけて見せますが、「今は自分が牽引したいくらいの気持ちです」とも話してくれます。後編は、その具体的な取り組みについて伺います。