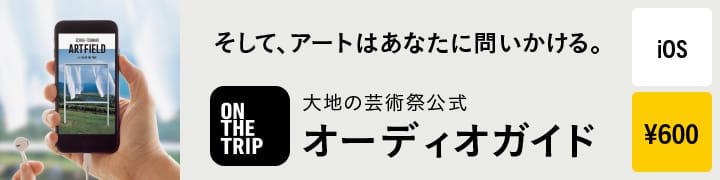アケヤマ -秋山郷立大赤沢小学校-

※2026年2月28日(土)は、シンポジウム「都市と山、共に生きる方法を考える」のため、一般の作品鑑賞は13:00までとなります。
人間が生きるために必要な術を山から学ぶための新しい学校
かつて義務教育就学免除地域に指定された秋山郷で、何とか子供たちに教育を受けさせたいという地域の願いを受け、私設学校として大正13年に立ち上がった大赤沢小学校。その後は時代を経て普通教育の場として活用されてきたが、2011年に最後の児童が卒業し休校、2021年に正式に閉校した。2024年、その廃校を《アケヤマ -秋山郷立大赤沢小学校-》として「人間が生きるために必要な術を山から学ぶための新しい学校」をオープン。これは秋山郷で培われた生きのびる知恵や技術を、アーティスト、住民、研究者とともに探究し学び、その過程で発見された資料や成果物を展示し共有していくための継続的な場でありプロジェクト。作家の深澤孝史監修のもと、各作家は秋山郷の風習・文化の徹底的なリサーチを行い、作品を制作した。さらに2階の元体育館の場づくりには建築家の佐藤研吾が加わることで各展示ブースそのものが作品として具体化された。これからも継続的な学びの場であり続けるために開館中はさまざまなワークショップやトークイベントを開催していく。
監修:深澤孝史
会場構成:一般社団法人コロガロウ/佐藤研吾
▼アケヤマの理念
秋山郷で培われた知恵の数々は、暮らしの中の年中行事、遊びや仕事など1年の生活サイクルの中にすべて詰まっている。秋山郷は特有の自然的条件と社会的条件が重なり、山のあらゆるものを持続的に共有・活用していく技術が発達していった。そんな持続的に山を活用する技術を継承していくための装置として、重要だったのが秋山郷で続くさまざまな信仰行事。そのどれもが自然のサイクルと人間の生活を重ねて持続的に恩恵を得るための技術を学ぶ装置となっていた。
今、技術も信仰も近代化によって、多くは急速に失われつつある。しかし、そうした生きるために必要な技術は決して不必要になったわけではなく、むしろ変動していく社会や自然環境で生き延びるための知恵や技術としても、都市と自然の境界を管理する技術としても、他者と向き合うときの原初的な知恵という意味でも重要度が高まっている。「アケヤマ」は、そうした秋山郷の暮らしから失われつつある技術や知恵と再び戯れ、その過程で生まれたものを共有できる場所を目指していきたい。
▼アケヤマの目的
1. 山のくらしの技術や知恵を学ぶ場
アーティスト・住民・研究者などさまざまな人が自身の関心のもと秋山郷でのフィールドワークをおこない、その過程や成果の展示・活動・発信する。
2. 山のくらしの技術や知恵を共有する場
山の技術や知恵、素材や資料を共有する場所として開く。
3. 資料や素材の収集と保管
歴史・民俗資料にとどまらず、フィールドワークの成果物(=作品)やさまざまな山の素材、記憶、映像、文献などを収集・保管する。
常設展示作品・作家
■秋山に伝わる生きるための根源的な生活技術を語り継ぐ場所

深澤孝史《続秋山記行編纂室》
■動き続ける学びの場

一般社団法人コロガロウ/佐藤研吾
■山の素材と技術の継承

井上唯《ヤマノクチ》
■マタギたちと動植物との間に内在した「語られざる物語」

永沢碧衣《山の胎》
■地域信仰や風習から未来のケアのあり方を考える
_MG_4336_1-1.jpg)
内田聖良《カマガミサマたちのお茶会:信仰の家のおはなし》
■越後妻有の樹木を用いた彫刻作品

山本浩二《フロギストン》
■秋山郷の樹木を画材として描きだす木々の総体としての山

山本浩二《胸中山水 秋山郷図》
これまでに開催したイベント、ワークショップ
■シンポジウム、トーク
2024年
●ティム・インゴルド(社会人類学者)講演「世界の中の秋山郷」
●白水智(日本史研究者)トークセッション「秋山の未来を語る」
■ワークショップ
2024年
●井上唯 ヤマノクチ部
井上唯によるプロジェクト「ヤマノクチ部」では、秋山郷で古くから親しまれている山の自然素材を集め、活用し、習俗の再生をするさまざまな活動を行う。希望者は「ヤマノクチ部」の部員として登録し、興味のある活動に申し込むことができる。
●内田聖良「ミニカマガミサマづくり」「秋山信仰体験」
●佐藤研吾「秋山郷を散歩して測る」
●永沢碧衣「山の胎でものがたり」
●深澤孝史「廃村甘酒村の悲願の田んぼの稲刈り」2025年
●井上唯 ヤマノクチ部
2024年から継続する「ヤマノクチ部」の活動。活動を通してつながった部員たちが山の暮らしの知恵を共有しあうなど緩やかなコミュニティが生まれている。2025年の主な活動は「草から糸を作る」「アンギンづくり」「トチの実を食べる」ほか
●深澤孝史「秋山郷のクロモジで枚カンジキを作ろう!」「ワダラ猟のワダラを作ろう!」
●深澤孝史「雪山を歩く」
施設情報と地図
| 営業時間 | 2026/1/24(土)~3/8(日)の土日祝 10:00~15:00 |
|---|---|
| 料金・入館料 | 一般800円、小中学生400円 ※期間によっては作品鑑賞パスポートや共通チケットを販売 |
| 住所 | 新潟県中魚沼郡津南町大赤沢丁154(旧津南小学校大赤沢分校) |