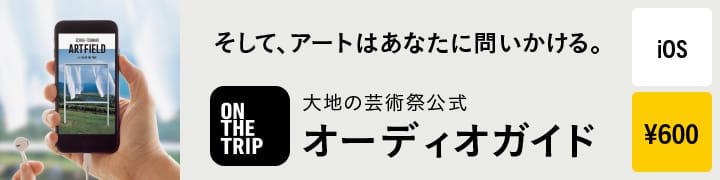芸術 / イリヤ&エミリア・カバコフ
イリヤ&エミリア・カバコフ「手をたずさえる塔」
イリヤ&エミリア・カバコフ「手をたずさえる塔」(2021年)Photo Nakamura Osamu
芸術 / イリヤ&エミリア・カバコフ
イリヤ&エミリア・カバコフ「手をたずさえる塔」

イリヤ&エミリア・カバコフ「手をたずさえる塔」(2021年)Photo Nakamura Osamu
《手をたずさえる塔》完成 ――《カバコフの夢》が完結する
テキスト・編集:アートフロントギャラリー
22 December 2021
2021年12月11日、イリヤ&エミリア・カバコフの《手をたずさえる塔》が竣工し、その記念イベントが開催されました。
カバコフは2000年、第1回「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」に参加、米づくりの過程を詩と彫刻で表現し、妻有の人々の労苦と生を寿いだ《棚田》は、大地の芸術祭を象徴する作品となりました。その後も、2015年には《人生のアーチ》が制作され、昨年からは《カバコフの夢》プロジェクトが構想され、今年7月には新作4点がまつだい「農舞台」で、1点が越後妻有里山現代美術館 MonETで公開されました。《手をたずさえる塔》はその集大成となり、新旧あわせ全9点からなる《カバコフの夢》が完成したのです。
コロナ禍だからこそ実現した《カバコフの夢》

「手をたずさえる塔」(2021年)Photo Nakamura Osamu
カバコフから《手をたずさえる塔》の提案があったのは、世界中で新型コロナウィルスが拡がり始め、ロックダウンや緊急事態宣言が相次いでいた昨年6月9日のことでした。《手をたずさえる塔》は、世界が分断され、寛容の精神が失われていく中で、「人々のつながりを表すモニュメント、人々がお互いの違い、彼らの問題、関心については平和的に話し合うのを促すためのモニュメント」でした。世界や地域の人々の喜怒哀楽によって光が色を変えるその塔は、大地の芸術祭総合ディレクター、北川フラムにオランダの歴史家ホイジンガが『中世の秋』で記した「或る時は悲しみを、或る時は喜びを告げ知らせる」教会の鐘の音を想起させるものでした。第8回の大地の芸術祭の作家も予算もすでに決定していましたが、その制作を決断しました。
同じ頃、昨年6月にスタートしたインスタグラムプロジェクト「Artists’ Breath」で、カバコフは「この状況にはまったく驚いていません。アーティストは孤独に慣れています。この状況は、よりもっとクリエイティブになるチャンスであり、自らの想像力を駆使して、この世界をより美しく、面白い場所にしていきたい」と語っています。それは、文化統制下の旧ソ連で発表するあてのない「自分のための作品」を制作し続けたカバコフならではの言葉でした。
《手をたずさえる塔》の提案は、困難な状況の中で夢を見、作品を創り続けたカバコフの「夢のアーカイブ」を越後妻有に作るプロジェクトへと発展し、《カバコフの夢》が構想されました。そしてカバコフの研究者で《人生のアーチ》のコーディネートをしていただいた鴻野わか菜さんをキュレーターに、建築家・利光収さん、田尾玄秀さんを設計者に迎え、カバコフと膨大なやりとりをしながらプロジェクトは進行していきました。
今年4月には、夏に開催予定だった大地の芸術祭の来年への延期が決定されましたが、プロジェクトは中断することなく、光のアーティスト・髙橋匡太さん、地元の高橋組、担当者等との協働作業により、《カバコフの夢》は完成に至りました。「世界がコロナ禍にあった2021年だったからこそできた」と北川は振り返ります。

プロフィール
イリア&エミリア・カバコフ
ロシア
イリヤは1933年、旧ソ連(現ウクライナ)生まれ。ニューヨーク在住。1950-80年代は公式には絵本の挿絵画家として活躍する一方で、非公式の芸術活動を続けた。80年代半ばに海外に拠点を移し、ソ連的空間を再現した「トータル・インスタレーション」をヴェネツィア・ビエンナーレ、ドクメンタ等に出展。1988年に、エミリア(1945年生)とのコラボレーションを始める。日本でも「シャルル・ローゼンタールの人生と創造」展(1999年)、「私たちの場所はどこ?」(2004年)、「イリヤ・カバコフ『世界図鑑』絵本と原画」展(2007年)等の個展を開催し、妻有では2000年「棚田」、2015年「人生のアーチ」を恒久設置した。2008年、高松宮殿下記念世界文化賞受賞
Photo : Roman Mensing / artdoc.de

「棚田」(2000年)

「人生のアーチ」(2015年)Photo Nakamura Osamu
城山にたたずむ世界と交信する塔
《手をたずさえる塔》の基礎台座部分は展示室になっており、《人生のアーチ》の5つの像、そして彫刻にはない天使の像を描いた6枚の油彩の複製、そしてカバコフが2005年から取り組んでいる《手をたずさえる船》の模型が展示されています。

「手をたずさえる船」(2021年)※模型展示
Photo Nakamura Osamu

塔の内部に展示された「人生のアーチ」の油彩の複製 photo Nakamura Osamu
《手をたずさえる船》は、カバコフがデザインした船の上で世界中の子どもたちの絵を組み合わせて帆をつくり、子どもたちが創作や交流を通じて多様な文化や思想の尊重を学ぶ場をつくることを目的とした《手をたずさえる塔》の姉妹的作品で、これまでエジプト、イタリア、スイス、アラブ首長国連邦、キューバ、アメリカ、ロシアなどで実施されてきました。
塔の内部は、展示だけでなく、音楽を聴いたり、思索の場となり、塔の周囲は小公園として整備され、人々の憩いや語らいのための場所となる予定です。

《手をたずさえる船》実際のプロジェクト
Photo Daniel Hegglin
オープニングセレモニーでは、大地の芸術祭実行委員長である関口芳史十日町市長が「大地の芸術祭の象徴である松代・城山にカバコフさんの3つ目の作品が誕生し、あたかも“カバコフ・ワールド”のようです。カバコフの精神が結実した作品群を来年の大地の芸術祭で全国、世界の人々に評価していただくことを思うとわくわくします」と述べ、北川ディレクターは、「この塔は、宇宙と交信する実験室のようでもあり、聖堂のようでもあります。城山を散策する中で「何か不思議な建物があるな」と興味を持ってもらいたい」と語りました。

ニューヨークのカバコフからはビデオで次のようなメッセージが送られてきました。
「私達はこの彫刻を作ることを、長い間夢見ていました。そしてついに、日本にいる友人たちの助力によって、越後妻有で実現されることとなりました。それは想像以上のものになりました。(…)《手をたずさえる塔》は、越後妻有だけに限られたプロジェクトではなく、普遍的なプロジェクトです。私たちはこのプロジェクトが光や希望、夢をもたらし、もっと面白く、もっと平和で、世界中の人々にとって普遍的なものになることを願います。私たちの夢を実現するのを助けてくださった皆さんに心から感謝しています」

シンポジウム「カバコフの夢――生きのびるためのアート」
オープニングを記念して開催されたシンポジウムには、地元住民だけでなく、在日ロシア人含め、全国から多くの人が参加、会場の農舞台《黒板の教室》(河口龍夫作品)は、《カバコフの夢》の完成を共に祝いたいという人々の熱気にあふれていました。

シンポジウムの様子
冒頭で北川ディレクターは、「今日の世界では、固有の空間と時間をもったサイトスペシフィックなアートがますます重要な位置を占め、民族や年代の違う人々がアートを媒介に出会うことの意味が大きくなってきました。それゆえに《手をたずさえる塔》の完成を機としたこのシンポジウムは<足元は大地に、目は遠く世界へ>という大地の芸術祭の志をあらためて確認する場となるでしょう」と述べました。
続いて、鴻野わか菜さん(早稲田大学教授)が、1933年旧ソ連(現ウクライナ)に生まれてからこれまでのカバコフの歩み、越後妻有に出会い9つの作品を実現するに至る過程とそれぞれの作品について紹介しました(今年7月、MonET、農舞台リニューアルオープン時の鴻野さんの寄稿もあわせてお読みください。
ロシア文化を専門とする鈴木正美さん(新潟大学教授)は、「カバコフと非公認芸術」と題し、ソ連時代のカバコフの活動について語りました。カバコフの著書『1960年代〜70年代…モスクワにおける非公式の生活に関する覚え書き』(1999)を引用しながら、明らかにされたのは、厳しい文化統制下、閉塞した状況にありながらも、アトリエや住居に毎晩のように集まり、議論し、酒を酌み交わし、歌い、詩を朗読し、「地下の文化」を花開かせていった芸術家たちのエネルギーであり、さまざまな芸術家、詩人、音楽家たちと交流し、実験的なパフォーマンスや集団行為に積極的に参加する前衛芸術家としてのカバコフの姿でした。
「毎日、夜に飲み会をしながら、どれほどの思想や出来事、問題について議論しただろうか。(…)何かとても幸せな気持ちで、興奮しながら新しい出来事について語り、何かを分かち合い、〈議論した〉。これこそがこの時代全体にわたって呼吸し、存在し、仕事することをわれわれに許していた幸せな空気だ。」(同書より)
美術評論家の暮沢剛巳さん(東京工科大学教授)は、東西冷戦下の旧ソ連においてカバコフがいかにして西側の動向に接して影響を受け、西側で評価されてきたのかについて語りました。
1950年代の「雪解け」の時代、西側の先端的な美術に接したカバコフは、以後、文化人類学者レヴィ・ストロースの「神話素(ミフエーマ)」、コンセプチュアルアート、アプロプリエーションアートなど、西側の動向に敏感に反応して自作に取り込み、モスクワ・コンセプチュアリスムを代表する作家となっていきます。1985年以降、ペレストロイカによって西側諸国での活動が可能となると、国外での活動を本格化させ、西側に拠点を置くと、自らのルーツである旧ソ連的な要素を強くとどめた「トータルインスタレーション」を制作していきました。インスタレーションによる2次元の空間化を試みるその作風は、即物的でありながら強い物語性を持ち、抽象表現とコンセプチュアルアートという20世紀美術の二大潮流をいずれも深い次元で体現するものあり、カバコフは「東西の十字路に立つ作家」として高く評価されています。
最後に、なぜカバコフは越後妻有にこれほどまでに思い入れを持つのか、越後妻有との出合いによってその作風はどのように変わったのかとの質問が会場の参加者からありました。それに対し北川ディレクターは、「カバコフが越後妻有を選んでくれたのは、ここをいい場所だと思っているからです。何よりも手伝っている人たちが一生懸命だからです。作品の意味も重要ですが、それをつくっていくプロセス、運営する仕組みにこそ意味がある。美術をつくっていくというのは並大抵なことではありません。行政とのたたかいもある。厳しい状況にありながらも、美術をインキュベートする場所が人々の中にある、それが妻有です」と答えました。
鴻野さんは「カバコフは西側に移住し、ソ連をテーマにし続けることに限界を感じていた中で、妻有に出合い、<労働>をテーマとした《棚田》を制作しました。それは世界のあらゆる場所に結び付きうる、今後の可能性を感じた作品だったのだと思います」と発言しました。
※シンポジウムの抄録は、『カバコフの夢』(現代企画室刊)改訂版に掲載される予定です。
海を介してつながるロシア
シンポジウムの後には、越後まつだい里山食堂でロシア料理や音楽を愉しみながらのレセプションが開催されました。

オープニングレセプションの様子@越後まつだい里山食堂



エウゲーニ・ウジーニンさんによるロシア音楽の歌と演奏
越後妻有にはカバコフの作品の他にも、2000年の芸術祭に参加したフランシスコ・インファンテの≪視点≫が芝峠温泉にあり、奴奈川キャンパスにはターニャ・バダニナの≪レミニッセンス(おぼろげな記憶)≫があります。2018年の芸術祭では、アレクサンドル・ポノマリョフによる≪南極ビエンナーレ– フラム号2≫の展示とシンポジウムも行われました。新潟にはロシア領事館もあり、古来、ロシアは最もゆかりのある国のひとつですが、「近くて遠い国」と感じる人も多いのが現況です。
来年の大地の芸術祭では、ヨーロッパ最大の美術館であるモスクワの「プーシキン美術館」の展覧会がMonETで開催予定です。隣国ロシアの人々との豊かな関係に向けて、大きな一歩が踏み出されました。