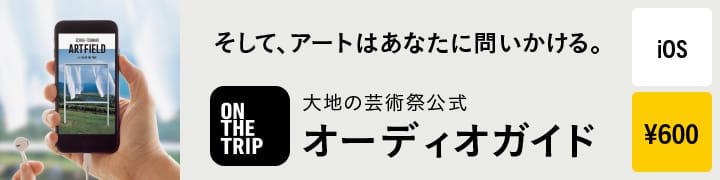芸術 / ブルック・アンドリュー
ディラン・ンラングー山の家(オーストラリア・ハウス内)
ブルック・アンドリュー「ディラン・ンラング-山の家」(2012年)Photo by NAKAMURA Osamu
芸術 / ブルック・アンドリュー
ディラン・ンラングー山の家(オーストラリア・ハウス内)

ブルック・アンドリュー「ディラン・ンラング-山の家」(2012年)Photo by NAKAMURA Osamu
たくさんのエッジをつなげた時、巨大なネットワークができあがる――オーストラリア・ハウス設立から8年。シドニー・ビエンナーレ・アーティスティック・ディレクター、ブルック・アンドリューが語る
テキスト・編集:アートフロントギャラリー
01 December 2020
11月1日、秋空の下、オーストラリア・ハウス「秋の会」が催され、浦田集落の人々、こへび隊、NPOスタッフが冬に向けた準備とともに、これからのオーストラリア・ハウスについて話し合いました。その会にあわせ、2012年、作品「ディラン・ンラングー山の家」をオーストラリア・ハウスのために制作したブルック・アンドリューにオンラインでインタビューを行い、越後妻有での経験、そして彼がアーティスティック・ディレクターをつとめ、先ごろ閉幕したシドニ・ービエンナーレ2020について伺いました。
――現在のオーストラリアでのコロナ禍の状況はどうですか?
今日(10月26日)は感染者ゼロでした。数字はずっと低くて、最高で700人。感染者数は本当に少ないです。
――越後妻有ではこの6月までは外から人が入りにくい状況が続きましたが、それ以降、外部にも開かれて、秋からは「オーストラリア・ハウス」も宿泊施設として再開しました。
素晴らしい。僕もいつか戻りたいな。
――オーストラリア・ハウスはあなたにとってどのような経験でしたか。
オーストラリア・ハウスで集落の人々、建築家のアンドリュー・バーンズ、越後妻有チームと一緒に制作したことは、とても楽しい思い出です。集落のなかで制作するということは貴重な経験でした。皆さんが土地や建物を維持するだけでなく、地域そして世界と文化的なつながりを持ち続けようとしてきたことは、信じられないことです。オーストラリア・ハウスは小窓のあるとても美しい建物で、2012年に完成した時は興奮しました。その時はアーティストのアンドリュー・リワルドやキュレーターのユランダ・ブレアもいました。集落の人々と一緒にいると謙虚な気持ちになりましたね。山に自生する食材を採りに行って、アンドリュー・リワルドと一緒に料理をふるまったりもしました。本当に楽しい思い出があって、こんなに歳月が過ぎてしまったことが信じられません。

プロフィール
Brook Andrew(ブルック・アンドリュー)
1970年オーストラリア、シドニー生まれ。オーストラリア先住民族のひとつ、ウィラドゥリ・ネーション(ケルト人の祖先をもつ)の現代美術家。1996年から国内外で創作活動を実施し、2020年第22回シドニー・ビエンナーレ・アーティスティック・ディレクターに抜擢される。越後妻有では「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2012」に参加し、パーマネント作品となる。
【Photo by Jessica Neath】

アンドリュー・バーンズ・アーキテクト「オーストラリア・ハウス」photo by NAKAMURA Osamu

浦田集落の方々やこへび隊、地元サポーターとの雪囲いの様子(2020年11月)
――あれから8年がたったのですね。その間、アーティストやデザイナー、スナッフパペッツのようなパフォーマーたちも滞在し、オーストラリア・ハウスであなたの作品と共に素敵な時間を過ごしました。今日は、あなたがアーティスティック・ディレクターをつとめられたシドニー・ビエンナーレ(*1)について伺いたいと思います。あなたは先住民初のディレクターでした。
2012年にカナダのジェラルド・マクマスターが共同ディレクターをつとめているので、先住民という意味では彼が最初ですね。オーストラリアの先住民としては僕が最初になるわけですが、ちょっと遅すぎたと思いますね。国際展ではあるもののこれまではヨーロッパにフォーカスしていた。でも僕たちはアジア太平洋地域に生きているわけだから、前回、片岡真実さんが芸術監督をつとめたことはエキサイティングなことでした。
今回のビエンナーレは、先住民の哲学、政治的課題を埋め込み、それぞれの民族が交流する非常に重要な機会だったと思います。オープニングにはアボリジニの伝統的な儀式がもたれ、世界中の先住民が集いました。北海道アイヌのマユンキキも参加しましたが、オーストラリアのアーティストや住民と出会えたことは、彼女の文化的アイデンティにとっても、ネットワークにとっても重要だったと思います。さまざまな先住民たちが一か所に集い、返還や環境などをめぐって話し合い、つながることで、強力なコミュニティの感覚が生まれました。それは高く評価していいと思います。

女性ヴォーカルグループ、マレウレウのメンバーでアイヌ文化コーディネーターのマユンキキは、日本政府によって禁じられたタトゥーの歴史・文化を展示。
Mayunkiki with photography by Hiroshi Ikeda, SINUYE: Tattoos for Ainu Women, 2020. Installation view for the 22nd Biennale of Sydney (2020), Museum of Contemporary Art Australia. Commissioned by the Biennale of Sydney with generous support from Open Society Foundations, and assistance from NIRIN 500 patrons. Courtesy the artist. Photograph: Zan Wimberley.
*1
オーストラリアで2年に一度開催される現代アートの祭典。2020年は新型コロナウィルスのため、「Google Arts & Culture」と連携して展示をオンラインで公開中。
――今回のテーマは「NIRIN」。アボリジニの人々の言葉で「エッジ(周縁、端)」という意味ですね。どうしてこの言葉を選ばれたのですか。
オーストラリアをはじめ世界の多くの国や地域は植民地化された歴史をもっています。多くの美術館もヨーロッパの眼差しによってつくられている。とても複雑ではありますが、そこから、環境、癒し、協働といったいろいろな問題を見ようと思いました。参加するのは必ずしもアーティストに限りません。例えばカイリー・クウォンはオーストラリアの有名なシェフですが、彼女は先住民、非先住民ともに、コミュニティと強いつながりを持ち、さまざまなイベントを行っています。私たちをつなげるものが何かを考えたとき、それが「エッジ」だったのです。私たちはみんなエッジを持っている。たくさんのエッジをつなげた時、巨大なネットワークができあがる。それはアーティストやクリエイティブな人たち、コミュニティにインスピレーションを与え、つなぐ言葉であると思ったのです。「NIRIN」は私の母の出身、ウィラジュリの言葉です。こうした哲学のもとに、アーティスト主導、コミュニティ主導の取り組みが行われました。さまざまな協働の試み、官僚主義的な構造への挑戦でもありました。でもビエンナーレの関係者はとても協力的で、展覧会はエキサイティングなものになりました。

シドニービエンナーレ2020話題作、イブラヒム・マハマの巨大なインスタレーション。
Ibrahim Mahama, No Friend but the Mountains 2012-2020, 2020. Cockatoo Island.
Commissioned by the Biennale of Sydney with generous support from Anonymous, and assistance from White Cube. Courtesy the artist; Apalazzo Gallery, Brescia and White Cube, London / Hong Kong. Photograph: Zan Wimberley.
――世界中から100組を超えるアーティストが参加しました。大変なお仕事だったと思います。あなたはアーティストであり、キュレーターでもあるわけですが、それはあなたにとってどのような体験でしたか。
アーティストとコレクティブでは100組ですが、人で数えると少なくとも250人は関わっていますね。というのも今回はコミュニティも参加しているからです。
キュレーションにはある種の支配的なナラティヴやプロセスがあるので、私は自分のことをキュレーターとは呼んでいません。アーティスティック・ディレクターが幸せなのは、自分自身のパレットで、実にさまざまなメディアを使って絵を描くことができるからです。ディレクターのオファーを受けた時、最初に思ったのは、どのようにアーティストに権限を与えられるかということでした。ビエンナーレやトリエンナーレに参加することのストレス、そして喜び、複雑さを私は理解しています。時にそのプロセスは難しいこともあります。私自身の考えや哲学といったことではなく、アーティストの作品をどうつくるか、そのプロセスをどう鼓舞するかが重要でした。
アーティストが仕事をする場合、その過程で次々と新しいこと、新しいアイデアに導かれていくわけですが、今回私たちはそういう試みをしました。プロセスに対してオープンマインドで臨むことが大切だと思いますね。組織の場合、厳しい締め切りがつきものですが、アーティスト主導の展覧会の場合、ある程度、なりゆきにまかせて実践することが可能になるのです。パンデミックのおかげで会期が3~4か月のびたのはよかったです。

大地の芸術祭2012に参加したアンドリュー・リワルドは庭のプロジェクトを行った。
Andrew Rewald, Alchemy Garden, 2019-20. Installation view for the 22nd Biennale of Sydney (2020), National Art School. Commissioned by the Biennale of Sydney with generous assistance from Create NSW. Courtesy the artist. Photograph: Zan Wimberley.
――今回、シドニー・ビエンナーレでは“ヴァーチャル・ビエンナーレ”を実現させましたね。
ラッキーだったのは、オープニングを一般公開できたことです。世界中の先住民を迎えたフォーラムを開催し、多くの人を町に迎えることができました。ほとんどのアーティストが来ることができ、圧倒的でした。パンデミックがこのエネルギーをつくりだし、私たちはビエンナーレのすべてを記録しなければいけないと思ったんです。会場の中を歩くようにオンラインで作品を見られるようにしました。アーティストトークやディスカッションもYouTubeで流しました。再開後はオーストラリアにいる人たちしか見に来れなかったわけですが、ビエンナーレを懸命に公開し続けたことは素晴らしいことです。おそらく最もよく記録されたビエンナーレのひとつではないでしょうか。オンラインですべての作品を見られるようにしたことで、一種の会話が生まれました。あなたたちのようにたくさんの人が作品を見てくれていることは嬉しい驚きです。オンラインでの経験はポジティブだったと思います。
――今回は多くのアーティストがいわゆるアートワールドには知られていない人で、アーティストでない人もいました。アートワールドからの反応はどうでしたか?
非常に興奮していました。それまで聞いたことのなかったアーティストとの出会いは驚きだったと思います。「アーティスト」という言葉はとても限定的です。英語あるいはヨーロッパの言語では「アートをつくる人」というひとつの意味しかない。でもそれは特殊なアイデンティのことであって、僕は「クリエイティヴ」という言葉を使いたいですね。今回は国際的に活躍する科学者たちも協働してくれました。
例えば、アラスカ出身のニコラス・ガラニン。彼のことは多くの人は知らなかったし、アメリカでも知られていませんでした。でも、人々は彼の作品を見てとても喜びました。それはアートスクールで学ぶことの枠を拡げ、アイデアや実践のあり方を刷新するようなものでした。

Nicholas Galanin, Shadow on the Land, an excavation and bush burial, 2020. Installation view for the 22nd Biennale of Sydney (2020), Cockatoo Island. Commissioned by the Biennale of Sydney with assistance from the United States Government. Courtesy the artist. Photograph: Jessica Maurer.
――「ブラックライブズマター(BLM)」運動が世界中に拡がっています。コロナ禍とBLMは現在私たちが直面している課題を明らかにしています。
その通りですね。国境や地域の境界、人と人との関係などいろいろなことが浮き彫りになっています。BLMは北アメリカから始まり、国際的な広がりを見せています。日本にもアフリカ系日本人がいますよね。オーストラリアでは「先住民の命も大切だ」運動が強力に進められ、BLMを通じて支持されています。拘留中に亡くなった黒人は400人もいて、先住民も含まれています。シドニー・ビエンナーレでもこうした悲しい社会の側面に光が当てられた、様々な背景をもった作品があり、シドニーにそうした運動を支持する雰囲気を醸成したと思います。コロナ禍は人々を分断することも、団結させることもある。人々を連帯させる、ポジティブな影響もあるのです。
オーストラリア・ハウス

Information
浦田地区にある、約150年の歴史をもつ家。遡れば江戸時代の後期から浦田を見つめてきたこの家が、2009年、オーストラリアと越後妻有の恒常的な交流拠点として新たな歴史を歩みだした。しかし、2011年3月の長野県北部地震で全壊。新たに建築しようと、審査員長に安藤忠雄氏を迎えた国際設計コンペは「小さくて、丈夫で、安い」建築。震災からの復興の象徴でもあり、建築の未来の一つの姿を示す本作が154点の応募から選ばれ、2012年に2代目「オーストラリア・ハウス」が誕生。2013年には、ヨーン・ウッツォン国際建築賞を受賞した。【庭制作=川口豊・内藤香織「庭が生まれるところ……そして」】
制作:2012年
開館:不定期/季節プログラムにあわせた開館 10:00~16:00(冬季は休館)
住所:新潟県十日町市浦田 7577-1
≫作品ページ