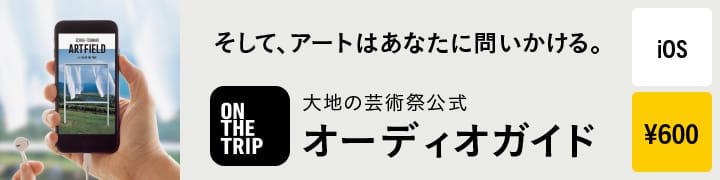物語 / 私と「大地の芸術祭」第2回(前編)
「うぶすなの家」誕生秘話 偶然に重なった中越地震と芸術祭

「うぶすなの家」スタッフ
小宮山マツノさん
「大地の芸術祭」を支える多様なサポーターにこの芸術祭を語っていただく本連載。今回のゲストは、十日町市の里山にある古民家レストラン「うぶすなの家」の名物スタッフ、小宮山マツノさんです。地域の食材を生かした料理と、名工たちによる多彩な焼き物に出会えるこの場所で、レストランを切り盛りするのは地元の「おんなしょ」(女衆)。マツノさんは2006年の「うぶすなの家」立ち上げ当初から参加されています。その経緯や、この家の物語を伺いました。
テキスト:中島晴矢 撮影:豊島望 編集:内田伸一、宮原朋之(CINRA.NET編集部)
あなたにとって大地の芸術祭とは?
人と出会える「心の財産」
05 November 2019
「うぶすなの家」誕生の舞台裏
2006年に開設された「うぶすなの家」
1924年築の茅葺き民家を「焼き物」と「料理」で再生した「うぶすなの家」。温もりのある建物に、陶芸家たちの手がけた囲炉裏やかまど、洗面台、風呂がしつらえられ、あちこちに陶器が並びます。何より目玉は、地元の食材を使った郷土料理を陶芸家の器で味わえるレストラン。そのスタッフの一人が、人懐っこい笑顔とおしゃべりで人気の小宮山マツノさんです。
「うぶすなの家」は2006年に誕生。マツノさんがここに関わるきっかけは、その2年前、2004年に起きた「新潟県中越地震」だったと言います。

芸術祭が始まった2000年当初は、各集落の大人たちも、正直、この催しをあんまり信用していませんでした(笑)。それにその頃、PTA活動などで地域の人たち同士がちょこっと会うことはあっても、奥底まで話をするほどの「地域性」って、この辺にはなかったんです。そんな時に、中越地震が起きました。そこでリーダーシップを発揮したのが、今では「うぶすなの家」の中心人物でもある、水落静子さんでした。

「うぶすなの家」スタッフのみなさん。左から、樋口道子さん(特集記事「折坂悠太が大切にする『ローカル』や『トラッド』の強さ」にご登場)、水落久子さん、小宮山マツノさん、そして皆のまとめ役的存在として知られる水落静子さん。
避難所で共に食事を作ったり寝起きしたりするなか、苦境を支え合う人々の間で地域のつながりが生まれていったそうです。

たとえ避難所であろうと、みんなで肩寄せ合えば幾晩でも過ごすことができるんだと、きっと村中の人が考えたと思いますよ。そうしたことがあった後、あの地震で被災して解体が決まっていたこの古民家を再生して活用しよう、という話が生まれました。これが本当に実現して2006年の第3回目の芸術祭から「うぶすなの家」がスタートしたんです。

2階には「光の茶室」(写真)や「闇の茶室」、「風の茶室」と呼ばれる空間があり、個性的な焼き物も展示されている。(撮影:大地の芸術祭)
もちろん起きなければよかったことには違いない地震と、動き出していた芸術祭。偶然に重なった「災害と祝祭」がきっかけとなり、地域の結びつきが強まったのです。なお、うぶすなは漢字で書くと「産土」。八百万の神様のお一人で、土地の守り神だそうです。「うぶすなの家」という名は、個性豊かな5人の陶芸家(澤清嗣、鈴木五郎、中村卓夫、吉川水城、加藤亮太郎)の焼き物が集い、土地の料理と地元の温かなもてなしがあるこの場所ならではのネーミングです。
この土地に根付く・芽吹く「新しい味」
この「うぶすなの家」のために小宮山さんたちがまずしたことは、この地域ならではの新メニュー開発だったそうです。

せっかくなら、地域で採れる山菜を生かして新しい名物料理を作ろうじゃないか、という話になったんです。それまでも山菜料理は当たり前に食べていたけど、スーパーの野菜が出始めてからは下火になっていました。そんな時期に「うぶすなの家」が始まることで、みんなで郷土料理を研究して作り上げていこう、となった。私は郷土の歴史や焼き物のことは詳しくないんですが、お料理の味に関しては得意なんです。
それから彼女たちは何回も寄り合って、会議や料理の試作を重ねます。そうして、ついに完成したのが「山菜ハンバーグ」と「山菜餃子」でした。

「山菜餃子」は最初に生まれたオリジナルメニューのひとつ。(撮影:大地の芸術祭)

日本列島のどこにもないハンバーグと餃子です。出来上がったときの嬉しさがまだ忘れられませんね。その後も、「こんな料理はどうだ」「こういうものも出せないか」と日々考えて、頭が空っぽになることはなかったですね。
「その気持ちよかったことぉ! 気持ちがでっかくなったっけねぇ」と明るい笑顔で語るマツノさんは、人と接することが大好きだそうです。

だから、実際にここがオープンしてお客さんが来てくれたら、ワクワクして嬉しくて。ああいうのを興奮するって言うんでしょうね。うちに帰ってからも「明日はどんな一日になるだろう」ってすぐ寝られないくらいで、落ち着かないから家の周りをぐるっと一周したりして(笑)。
「うぶすなの家」前での切腹ピストルズによる太鼓演奏(2018年の第7回「大地の芸術祭」)。囃子に合わせて踊り出すマツノさんたちの姿も。(撮影:uogaeru[佐藤正博])
以来10年以上、はつらつとした笑顔で人々を迎え続ける原動力を聞くと、マツノさんは「私は『ネアカ』ですから。おしゃべりで、まるでスイッチのない壊れたラジオ」と笑います。

外国の方が来てくれる時は、その国の言葉を真似して「ニイハオ」とか「シェイシェイ」なんて言うと、お客さんが反応してくれるんですよ。そして側に寄っていって、「ご飯、大盛り?」って身振り手振りで伝える。「きっと伝わったんだな」と思うと、それがまた堪らなくて。そうした交流が大好きですね。ここは本当に財産ですよ。私なんかにとっては、人と会えて嬉しいし、仕事にもなる。その両方があるから、毎日元気を作って届けられているんだと思います。

越後妻有の季節も感じながら郷土料理を楽しめるこの場所には、国内外から多くの人が訪れる。(撮影:大地の芸術祭)
住み慣れた集落にいながら、多様な人々と出会える職場。そんな「うぶすなの家」で人々を迎え入れる仕事は、小宮山さんにとって天職に違いありません。後編では、越後妻有での日常の暮らしが、芸術祭とどうつながっているのかを伺います。